看護師の皆さん、日々の業務お疲れ様です!💉
多くの看護師が臨床現場での活躍を目指す一方で、看護の質を向上させ、未来を切り開く「看護研究者」というキャリアパスがあるのをご存知でしょうか?

看護研究者って、なんだかスゴそう!✨
難しそうだけど、どんなお仕事なのかな?🤔 ワクワクしてきた!
この記事では、看護研究者の役割、必要なスキル、キャリアパス、そしてその魅力まで、徹底解説します!
記事を読むことで、新たなキャリアの可能性を知り、自身のスキルアップやキャリアプランに役立てることができるでしょう。
転職を考える上で、研究という道も選択肢の一つになるかもしれません。
1. 看護研究者とは?仕事内容を具体的に解説
看護研究者は、看護実践の質の向上を目指し、科学的な手法を用いて様々な課題に取り組む専門職です。
臨床現場での疑問や課題を解決するためのエビデンス(科学的根拠)を生み出すことが主な役割となります。
具体的な仕事内容は多岐にわたりますが、主なものとして以下が挙げられます。
- 研究テーマの設定: 臨床現場での観察や経験、既存の文献、社会的なニーズ(例:厚生労働省が示す重点領域など)に基づき、探求すべき課題を見つけ、研究テーマを設定します。
- 研究計画の立案: 設定したテーマに対し、目的を明確にし、どのような方法(調査、実験、インタビューなど)でデータを収集・分析するのか、倫理的な配慮は十分かなどを詳細に計画します。
- データ収集と分析: 研究計画に沿って、対象者へのアンケート配布・回収、インタビューの実施、実験、文献調査などを行い、必要なデータを集めます。集めたデータは統計学的手法などを用いて客観的に分析し、意味を解釈します。
- 研究成果の発表: 分析結果をもとに、研究の意義や結論を論文としてまとめ、学会や学術雑誌で発表します。これにより、研究成果が他の研究者や実践家と共有され、知識が蓄積されていきます。
- 研究成果の活用推進: 研究で得られた知見が、実際の看護ケア改善に繋がるよう、研修会での発表やガイドライン作成への協力などを通じて、臨床現場への橋渡しを行います。
- 教育・指導: 大学や大学院などで、後進の研究者や看護学生に対して、研究方法論や専門知識に関する教育・指導を行います。


現場の「なんでだろう?」が研究の始まりになるんだね!🤔
データを集めて分析して…なんだか探偵みたいでカッコいいかも✨
厚生労働省とかの情報も参考にするんだね!
2. 看護研究者の役割と貢献:医療現場にもたらす変革
看護研究者の活動は、目に見えにくいかもしれませんが、医療現場や社会全体に大きな貢献をしています。
その中心にあるのが「エビデンスに基づいた看護(EBN: Evidence-Based Nursing)」の推進です。
- より安全で効果的な看護ケアの開発: 褥瘡予防の新しいケア方法、転倒リスクの高い患者さんへの介入策、効果的な疼痛管理の方法など、研究によって効果が証明されたケアを開発・導入することで、患者さんの安全を守り、ケアの質を高めます。
- 患者QOL(生活の質)の向上: 治療による副作用の軽減策、慢性疾患を持つ人のセルフケア支援プログラム、終末期における意思決定支援など、患者さんとその家族がより良い生活を送るためのケアを探求します。
- 看護業務の効率化と改善: 看護師の業務負担を軽減するためのタスクシフトに関する研究や、効率的な情報共有システムの開発・評価などを通じて、働きやすい環境づくりにも貢献します。
これは転職を考える一因となる労働環境の問題解決にも繋がる可能性があります。 - 医療政策への影響: 看護現場の実態やケアの効果に関する研究データは、客観的な証拠として、看護師の人員配置基準の見直しや、特定の看護分野(例:在宅看護、精神科訪問看護など)への診療報酬改定、国の保健医療政策の立案などに影響を与えることがあります。(例:日本看護協会による政策提言活動など)
- 看護学の発展: 新たな知見を生み出し、看護理論や看護モデルを発展させることで、看護という専門分野自体の深化に貢献します。
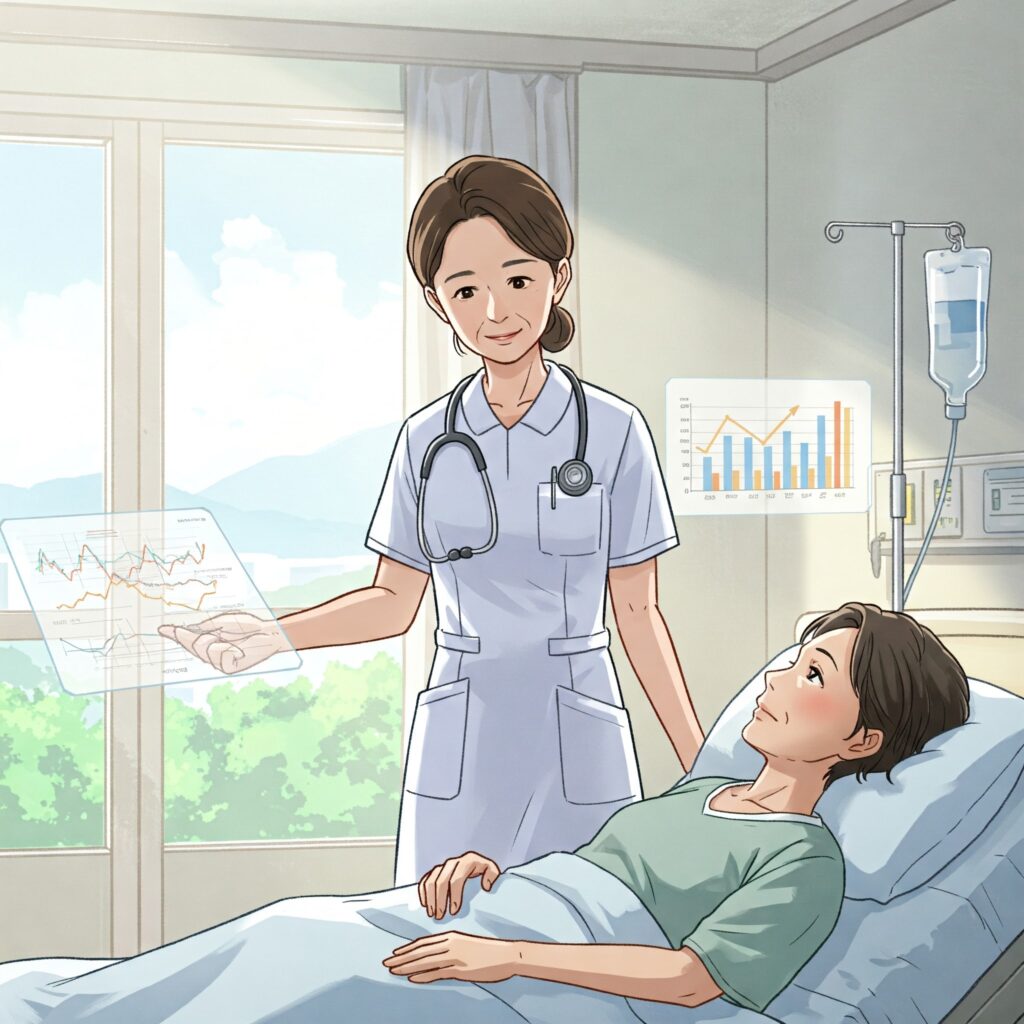

研究って、ただ論文を書くだけじゃないんだ!
患者さんのため、看護師さんのため、そして社会のためにもなってるんだね。すごい!💪
EBNって大事なんだなあ。
3. 看護研究者になるには?必要なスキルと資格
看護研究者としてのキャリアを歩むためには、一般的に看護師としての臨床経験を経た上で、大学院に進学し、専門的な教育を受けることが標準的なルートです。
- 必要な学歴・学位:
- 修士(看護学): 大学院の修士課程(博士前期課程)を修了すると得られます。研究の基礎(研究デザイン、統計、倫理など)を学び、指導教員のもとで研究プロセスを一通り経験し、修士論文を作成します。
研究職への第一歩となります。 - 博士(看護学): 大学院の博士課程(博士後期課程)を修了すると得られます。自立した研究者として、独創的な研究テーマを設定し、質の高い研究を遂行・完成させる能力が求められます。
大学教員や研究機関の専門職を目指す場合に、有利になることが多い学位です。
- 修士(看護学): 大学院の修士課程(博士前期課程)を修了すると得られます。研究の基礎(研究デザイン、統計、倫理など)を学び、指導教員のもとで研究プロセスを一通り経験し、修士論文を作成します。
- 必要な資格:
- 看護師免許: 看護研究の基盤となる必須の資格です。
- 求められる能力・スキル:
- 探求心と論理的思考力: 常に疑問を持ち、物事を深く考え、筋道を立てて客観的に分析する力。
- 情報リテラシー: 膨大な情報の中から信頼できる文献やデータを効率的に探し出し、批判的に吟味する能力。
- 研究遂行能力: 研究計画の立案、データ収集・分析、論文作成という一連のプロセスを遂行するスキル。
統計ソフト(SPSS、Rなど)の知識も役立ちます。 - コミュニケーション能力: 研究協力者(患者さん、臨床スタッフなど)との良好な関係構築、研究チーム内での連携、学会発表での質疑応答など、多様な場面で必要とされます。
- 文章表現力: 研究成果を正確かつ明瞭に伝えるための日本語および英語のライティング能力。
- 語学力(特に英語): 最新の国際的な研究動向を把握するため、英語論文の読解は必須です。
国際学会での発表や海外研究者との交流を目指すなら、会話力も重要になります。 - 高い倫理観: 研究対象者の人権擁護、プライバシー保護、インフォームド・コンセントの取得など、研究倫理指針を遵守する姿勢。
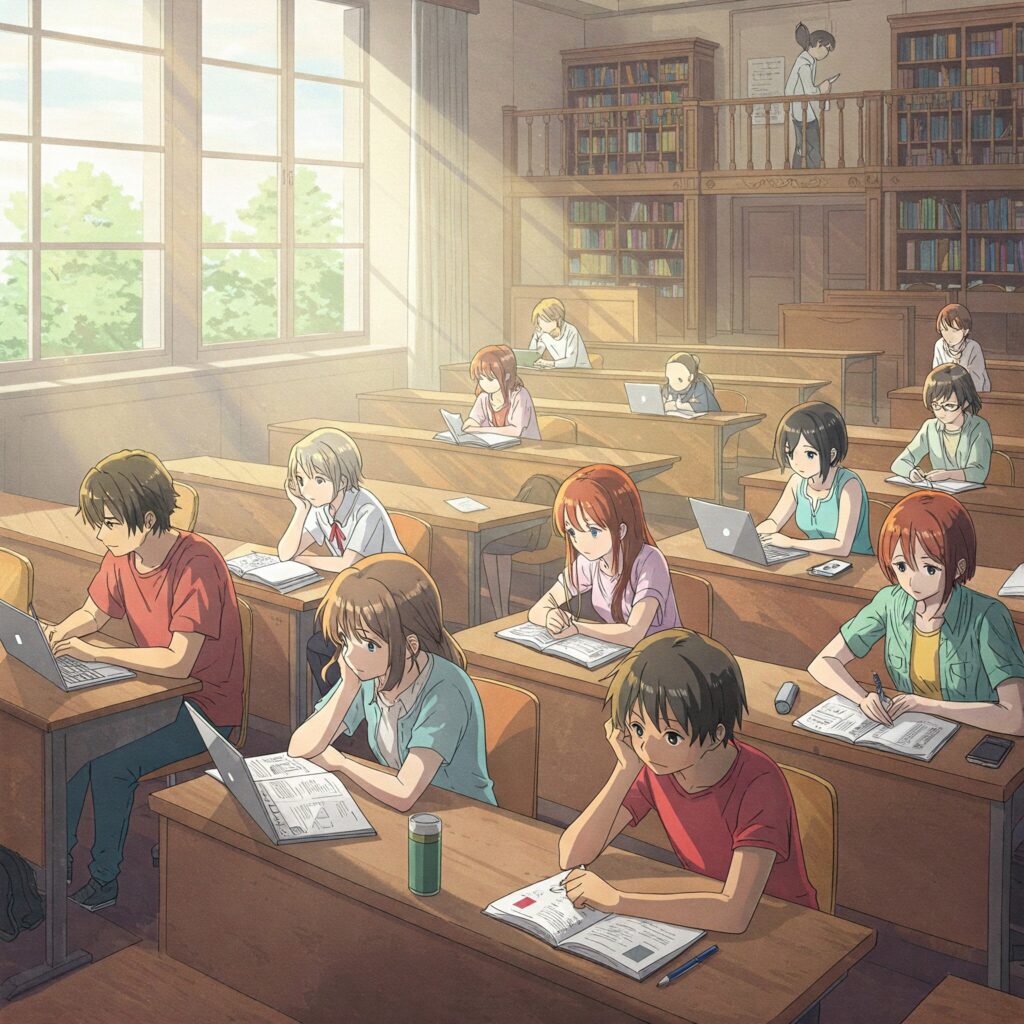

やっぱり大学院進学がカギなんだね!
修士と博士…目標に合わせて選ぶ感じかな🤔
スキルもたくさん必要だけど、一番大事なのは「知りたい!」っていう気持ちかも!
英語もコツコツ頑張らないとだね💦
4. 看護研究者のキャリアパス:専門分野と成長の機会
看護研究者の活躍の場は、大学だけにとどまりません。
大きく分けて以下の3つのフィールドが考えられます。
- 教育機関(大学、短期大学、専門学校など):
- 役割: 看護学生や大学院生の教育、自身の専門分野の研究、論文執筆、学会発表、大学運営への参画など。
- キャリア: 助教、講師、准教授、教授といったアカデミックポストを目指します。
教育と研究の両立が求められます。
- 研究機関(大学附置研究所、国公立の研究センター、企業の研究所など):
- 役割: 特定の研究領域に特化し、専門性の高い研究プロジェクトに従事します。
- 厚生労働省所管の研究所や、国立がん研究センター、国立循環器病研究センターなどが例として挙げられます。
- キャリア: 研究員、主任研究員、部長など、機関独自の役職があります。
研究成果を出すことが重視される傾向にあります。
- 役割: 特定の研究領域に特化し、専門性の高い研究プロジェクトに従事します。
- 臨床現場(病院、クリニック、訪問看護ステーションなど):
- 役割: 臨床実践を行いながら研究活動にも携わる(クリニカル・ナース・サイエンティスト)。
現場の課題解決に直結する研究(臨床研究)を行い、その成果を速やかに実践に還元します。
また、院内の研究活動の推進や、他のスタッフへの研究指導を行うこともあります。
専門看護師(CNS)や認定看護師(CN)がこの役割を担うことも多いです。 - キャリア: 研究支援部門の担当者、研究担当の看護管理者、専門看護師/認定看護師としてのキャリアアップなどが考えられます。
転職後、臨床経験を活かしながら研究に携わる道として注目されています。
- 役割: 臨床実践を行いながら研究活動にも携わる(クリニカル・ナース・サイエンティスト)。
専門分野: 基礎看護学、成人看護学、老年看護学、小児看護学、母性看護学、精神看護学、地域・在宅看護学、看護管理学、がん看護、感染管理、災害看護など、非常に多岐にわたります。
自身の関心や臨床経験に基づいて専門性を深めていきます。
成長の機会: 国内外の学会参加、論文発表、研究費獲得(科研費など)、共同研究、研修会への参加などを通じて、常に最新の知識・技術を学び、研究者としてスキルアップし続けることができます。


大学の先生だけじゃないんだね!😮
病院で働きながら研究できる道もあるなんて、現場が好きな人には魅力的かも!
専門分野もいっぱいあって、自分の興味を追求できそう✨
5. 看護研究者のやりがいと魅力:未来を創る仕事
看護研究は、時に地道で根気のいる作業ですが、それを乗り越えた先には大きなやりがいと魅力があります。
- 看護実践への貢献実感: 自分の研究がきっかけでケアが改善され、患者さんの回復やQOL向上に繋がったと実感できた時の喜びは格別です。
「ありがとう」の言葉が研究成果を通して間接的に届くこともあります。
- 知的好奇心の探求: 臨床現場での素朴な疑問や課題に対し、「なぜ?」「どうすればもっと良くなる?」と深く探求し、真実や解決策を発見していくプロセスそのものが大きな魅力です。
- 未来の看護を創造する: 現在のケアを改善するだけでなく、数年後、数十年後を見据えた新しい看護のあり方や技術を提案し、形にしていくことができます。まさに看護の未来を創る仕事です。
- 専門性の深化と自己成長: 特定の分野を深く掘り下げ、高度な専門知識とスキルを習得できます。
研究活動を通して、論理的思考力や問題解決能力など、様々な能力が磨かれ、継続的な自己成長を実感できます。
- 自律性と柔軟性: (所属機関によりますが)研究テーマやスケジュールの裁量権が比較的大きく、自律的に仕事を進めやすい側面があります。
ライフスタイルに合わせて働き方を調整しやすい場合もあります。
- 多様なネットワーク: 学会や研究会を通じて、国内外の様々な分野の研究者、臨床家、他職種と交流する機会があり、刺激を受けながら視野を広げることができます。


自分の研究が未来の看護を作るなんて、すごいロマンがある!✨
大変なこともたくさんありそうだけど、それ以上に「やってよかった!」って思える瞬間がたくさんありそう😊
知的好奇心が満たされるのも嬉しいね!
6. 看護研究者の現状と課題:今後の展望
看護研究の重要性はますます高まっていますが、その発展のためにはいくつかの課題も存在します。
現状と課題:
- 研究者の不足: 看護学の大学院は増えましたが、特に博士号を持ち、自立して研究を推進できる研究者の数はまだ十分とは言えません。教育・研究機関でのポストも限られています。
- 研究時間の確保: 臨床現場で働く看護師が、日々の業務に追われ、研究活動のための時間を確保することが難しいという現状があります。(日本看護協会などの調査でも指摘されることがあります)
- 研究資金の確保: 質の高い研究を行うためには、調査費用や物品購入費などの研究資金が必要ですが、競争的な研究費(科研費など)の獲得は容易ではありません。
- 研究成果の活用: 研究で得られた知見が、必ずしもスムーズに臨床現場の実践に結びついていない「研究と実践のギャップ」も課題として指摘されています。
- 学際的連携: 医師や他のコメディカルスタッフ、工学系研究者など、他分野の研究者との連携(学際的研究)が、今後の発展には不可欠ですが、まだ十分に進んでいない側面もあります。
今後の展望:
- 研究者育成・支援体制の強化: 若手研究者の育成プログラムの充実、研究に専念できる環境整備、研究相談・支援体制の強化などが期待されます。
- 臨床と研究の連携強化: 病院全体で研究を支援する体制づくりや、臨床にいながら研究活動を行いやすいキャリアパス(クリニカル・ナース・サイエンティストの育成・配置など)の確立が望まれます。
- 研究資金獲得支援: 国や財団からの研究助成の拡充や、研究費申請のサポート体制強化が重要です。
- DX(デジタル・トランスフォーメーション)の活用: 電子カルテデータの二次利用やAI技術の活用など、デジタル技術を駆使した効率的かつ大規模な研究の推進が期待されます。
- 国際共同研究の推進: 海外の研究者とのネットワークを強化し、国際的な視点での共同研究を活発化させることで、日本の看護研究のレベルアップに繋がります。


研究者の人がもっと増えて、研究しやすい環境が整うといいなあ🤔
臨床と研究がもっとうまく繋がれば、もっと良いケアが生まれそうだね!
未来は明るいと信じたい!✨
7. 看護研究者に関するよくある質問(Q&A)
Q1:看護師の臨床経験がなくても看護研究者になれますか?
A1:不可能ではありませんが、臨床経験がある方が、現場のニーズに基づいた研究テーマを見つけやすく、研究の意義を深く理解できるため、一般的には臨床経験を数年積んでから大学院に進学するケースが多いです。
臨床経験は研究の大きな強みになります。
Q2:看護研究者の給与はどのくらいですか?
A2:所属する機関(大学、研究所、病院など)や役職、経験年数によって大きく異なります。
一般的に、大学教員や専門の研究職の場合、経験を積むことで、臨床の看護師と同等以上の収入を得られる可能性がありますが、一概には言えません。
公的機関の給与規定や、各機関の募集要項などを参考にすると良いでしょう。
Q3:研究の仕事は、夜勤や不規則な勤務はありますか?
A3:大学や研究所での勤務は、基本的には日勤帯が中心で、土日祝日が休みの場合が多いです。
ただし、学会参加や研究の進捗によっては、時間外労働や休日出勤が必要になることもあります。
臨床現場で研究を兼務する場合は、所属先の勤務形態によります。
Q4:文系でも看護研究者になれますか?
A4:研究には統計解析など理系的な知識も必要になりますが、最も重要なのは論理的思考力や探求心です。
大学院では統計学なども基礎から学べますし、インタビュー調査など質的研究と呼ばれる手法もあり、文系出身者でも十分に活躍できます。
必要な知識は入学後に学ぶ意欲があれば問題ありません。
8. まとめ:看護研究者というキャリアを考える
看護研究者は、科学的根拠に基づいたケアを探求し、看護の質の向上と発展に貢献する、非常に専門性の高い仕事です。
日々の看護実践に疑問を感じたり、特定の分野をもっと深く学びたい、看護の未来を創る仕事に関わりたい、と考えている方にとって、魅力的なキャリアパスの一つと言えるでしょう。
大学院への進学など、時間や費用、学力的なハードルがあるかもしれませんが、その先には大きなやりがいと成長の機会が待っています。
転職を考える際に、臨床現場以外の選択肢として、ぜひ「看護研究」という道を検討してみてはいかがでしょうか。
看護研究者という道も素晴らしい選択肢ですが、ご自身の将来を考える上では、他の多様なキャリアパスも知った上で、総合的にキャリアプランを設計することが大切です。
以下の記事では、専門看護師・認定看護師、ジェネラリスト、管理職、企業など、看護師の多様なキャリアパスの紹介から、自己分析の方法、具体的なキャリアプランの立て方まで詳しく解説していますので、ぜひキャリア全体を考える参考にしてください。
-

-
【キャリアプラン設計】看護師の多様なキャリアパスを知って未来を描こう
「今の職場で働き続けるべきか迷っている…」 「将来どんな看護師になりたいか、具体的なイメージが湧かない…」 「もっと自分に合った働き方があるんじゃないか?」 看護師として日々忙しく働く中で、ふと立ち止 ...

看護研究者、奥が深くてやりがいのある仕事だね!✨
もし興味が湧いたら、まずは大学院の情報を集めてみるのが良いかも😊
新しい挑戦、応援してるよ!💪
参考文献・参考情報
この記事を作成するにあたり、以下のような信頼性の高い情報源に見られる情報を参考に、看護研究者に関する一般的な内容を構成しました。
特定の情報源の主張をそのまま掲載するのではなく、複数の情報を比較検討しています。
最新かつ詳細な情報(制度、カリキュラム、求人等)については、必ず各公式サイト等で直接ご確認ください。
URLは変更される可能性がある点にご留意ください。
- 日本看護協会ウェブサイト
- URL: https://www.nurse.or.jp/
- (参考にした主な関連情報例):
- 看護研究の倫理指針に関する情報
- エビデンスに基づいた看護(EBN)の推進に関する資料
- 看護研究に関する学会情報や研修案内
- 看護職のキャリアに関する情報 など
- 厚生労働省ウェブサイト
- URL: https://www.mhlw.go.jp/
- (参考にした主な関連情報例):
- 看護職員の需給や働き方に関する調査・検討会資料
- 科学研究費助成事業(科研費)など研究助成に関する情報
- 医療・介護分野における研究開発推進に関する情報 など
- 看護学系の大学・大学院ウェブサイト
- (URLは各大学・大学院のものを参照)
- (参考にした主な関連情報例):
- 大学院(修士・博士課程)のカリキュラム、研究指導体制
- 教員の研究分野・業績
- 入学試験要項、学費、奨学金制度
- 修了生のキャリアパスに関する情報 など
- 学術論文データベース
- CiNii Articles: https://ci.nii.ac.jp/
- J-STAGE: https://www.jstage.jst.go.jp/
- PubMed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
- (これらのデータベースを通じて、本記事で解説した看護研究者の役割、EBNの意義と実践、特定の看護分野における研究動向、研究者に求められるコンピテンシー、キャリアパスに関する調査研究など、学術的な裏付けとなる多数の研究論文にアクセスすることができます。)
- 看護研究に関する書籍・専門誌
- (例)日本看護研究学会: https://www.jsnr.jp/ (学会誌『日本看護研究学会雑誌』を発行)
- (例)医学書院 看護出版編集部: https://www.igaku-shoin.co.jp/journal/nursing (学術雑誌『看護研究』などを発行)
- (これらの専門誌や、看護研究の方法論(研究デザイン、統計解析、質的研究など)、研究倫理、特定の看護学領域の理論や最新知見を解説する教科書・専門書は、本記事の内容の基礎となる学術的知識や標準的な考え方を提供しています。)
- 各研究機関・病院のウェブサイト
- (URLは各機関・病院のものを参照)
- (参考にした主な関連情報例):
- 研究部門・研究センターの紹介
- 実施中の研究プロジェクト
- 研究職(看護職を含む)の公募情報
- 臨床研究・治験に関する情報、認定看護師・専門看護師の研究活動紹介 など
免責事項
本記事は、看護研究者に関する一般的な情報提供を目的として作成されたものであり、特定のキャリアパスや転職を保証・推奨するものではありません。
紹介した情報(必要なスキル、キャリアパス、給与水準など)は、個々の状況や所属機関によって異なります。
大学院のカリキュラムや入学要件、求人情報などの詳細については、必ず各大学、研究機関、病院などの公式サイトや募集要項をご確認ください。
最終的なキャリアの選択や判断は、ご自身の責任において行っていただきますようお願いいたします。
参照した情報源のURLは変更される可能性があります。