近年、男性の育児参加が社会的に推奨され、育児休業を取得する男性も増えてきました。
しかし、まだまだ男性が育児休業を取得することへのハードルが高いと感じる職場も少なくありません。
特に、24時間体制で患者さんの命を預かる看護師の世界では、「男性が育休?」という雰囲気や、人手不足から取得をためらってしまうパパナースも多いのではないでしょうか。
この記事では、そんな男性看護師(パパナース)の皆さんが、自信を持って育児休業を取得し、復帰後もキャリアと育児を両立しながら活躍するための情報を徹底解説します。
育児休業制度の詳しい内容から、取得に向けた準備、職場との交渉術、復帰後の働き方の選択肢、そして、どうしても今の職場では難しい場合の「転職」という選択肢まで、幅広くカバーしています。

こんにちは!ブロガーの御茶犬です✨
この記事が、育児と仕事の両立に悩むパパナースの皆さんにとって、一歩踏み出すためのヒントになれば嬉しいです!💪
一緒に見ていきましょう!
この記事を読めば、あなたのこんな疑問や不安が解消されるはずです。
さあ、一緒に男性看護師の育児休業取得と、その先の働き方について考えていきましょう。
看護師求人ジョブメドレー1. 男性の育児休業取得の現状と必要性
まずは、男性看護師を取り巻く育児休業の現状と、なぜ取得が必要なのかを見ていきましょう。
パパナースの育休取得率は?
厚生労働省の「令和4年度雇用均等基本調査」によると、男性の育児休業取得率は17.13%となり、過去最高を更新しました。
年々上昇傾向にはありますが、女性の取得率(80.2%)と比較すると、まだまだ低い水準です。
医療・福祉分野に限定したデータは限られますが、看護師を含む医療従事者は、依然として女性が多い職場であり、「男性が育休を取得する」という前例が少ない、あるいは理解が得られにくいという現状が推測されます。

なぜ男性看護師が育休を取得するべきなのか
男性看護師が育児休業を取得することには、多くのメリットがあります。
- 父親としての役割: 生まれたばかりの子どもと触れ合い、主体的に育児に関わることで、父親としての自覚と責任感が深まります。
これは、子どもの成長にとって非常に重要です。
- パートナーのサポート: 出産直後のパートナーの心身の負担は計り知れません。
育児休業を取得し、家事や育児を分担することで、パートナーの回復を助け、夫婦間の絆を深めることができます。
- 自身の心身の健康: 育児を通して、仕事とは違う充実感や学びを得られます。
また、一時的に仕事から離れることで、リフレッシュにも繋がります。
- チーム医療への貢献: 育児経験を通して、患者さんやその家族への共感力が高まり、より質の高い看護実践に繋がる可能性があります。
また、多様な働き方を認め合う職場風土は、チーム全体の活性化にも貢献します。
- キャリアへの好影響: 長い目で見れば、育児経験はマネジメント能力やコミュニケーション能力を高める機会にもなり得ます。
育休取得を阻む「壁」とは?
多くのメリットがある一方で、男性看護師の育休取得には以下のような壁が存在します。
- 職場の雰囲気: 「男性が休むなんて」「前例がない」といった無理解や、取得しにくい雰囲気。
- 人員不足: 看護師不足が深刻な職場では、自分が休むことへの罪悪感や、同僚への負担増を懸念してしまう。
- キャリアへの影響懸念: 昇進や異動に不利になるのではないか、復帰後に元の業務に戻れないのではないか、といった不安。
- 収入減への不安: 育児休業給付金だけでは、収入が減少することへの心配。
- 制度への理解不足: そもそもどのような制度があるのか、どうすれば利用できるのか知らない。

男性看護師さんの育休取得、まだまだハードルがあるんですね💦
でも、取得するメリットはたくさん!✨
特にパートナーのサポートは本当に重要ですよね。
これらの「壁」をどう乗り越えていくかがポイントになりそうです🤔
2. 【徹底解説】男性看護師のための育児休業制度
育児休業を取得するためには、まず制度を正しく理解することが重要です。
ここでは、パパナースが知っておくべき主要な制度について解説します。 (出典:厚生労働省 育児・介護休業法について など)
知っておきたい「育児・介護休業法」の基本
育児休業は、「育児・介護休業法」に基づいた労働者の権利です。
- 対象者: 原則として、1歳に満たない子を養育する男女労働者(日々雇用を除く)。
有期契約労働者も一定の要件を満たせば対象となります。
- 期間: 原則として、子どもが1歳になるまで(保育所に入れないなどの理由がある場合は、最長2歳まで延長可能)。
父母ともに育児休業を取得する場合は、「パパ・ママ育休プラス」制度により、子どもが1歳2か月になるまで延長できます。
- 申出: 原則として、休業開始予定日の1か月前までに、事業主に申し出る必要があります。
パパ・ママ一緒に!「産後パパ育休」とは?
2022年10月から「産後パパ育休(出生時育児休業)」が創設されました。
これは、従来の育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に最大4週間まで取得できる制度です。
- 分割取得可能: 2回に分けて取得できます。
- 申出期限: 原則、休業開始の2週間前まででOKです。
- 休業中の就業: 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能です。
パートナーの退院直後など、特にサポートが必要な時期に柔軟に休みを取得しやすくなりました。

収入面の不安を解消!「育児休業給付金」
育児休業中は原則として給与は支払われませんが、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。
- 支給要件: 雇用保険に加入しており、育児休業開始前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(ない場合は就業時間数が80時間以上の月)が12か月以上あることなど。
- 支給額: 原則として、休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%(育休開始から6か月経過後は50%)。
- ※産後パパ育休(出生時育児休業)の場合は、「出生時育児休業給付金」として、休業開始時賃金日額 × 休業日数 × 67% が支給されます(上限あり)。
- 申請方法: 原則として、事業主を通じてハローワークに申請します。
意外と知らない?「社会保険料の免除」
育児休業期間中(産後パパ育休含む)は、健康保険・厚生年金保険の保険料が、被保険者負担分・事業主負担分ともに免除されます。
- 手続き: 事業主が「育児休業等取得者申出書」を年金事務所または健康保険組合に提出します。
- 注意点: 免除期間中も、被保険者資格は継続され、将来の年金額計算においては、保険料を納付したものとして扱われます。

育休中の収入面、やっぱり気になりますよね!
育児休業給付金や社会保険料免除の制度をしっかり理解しておけば、安心して休業に入れますね👍
産後パパ育休は短い期間でも取れるのが嬉しいポイント😊
ここでは男性看護師の育児休業に焦点を当てて解説しましたが、女性の産前・産後休業(産休)を含めた制度全体や、育児休業給付金、社会保険料免除、さらには転職時の失業保険(雇用保険)について、より網羅的に知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。
-

-
知らないと損?看護師が使える産休・育休・失業保険の基礎知識【2025年最新版】
「そろそろ転職しようかな…」 「将来的に子どもも欲しいし、働き方を見直したいな」 看護師としてキャリアを重ねる中で、多くの方が転職やライフプランについて考えるタイミングがあると思います。 特に女性が多 ...
3. 育児休業取得に向けた準備と職場との交渉術
制度を理解したら、次はいよいよ具体的な準備と職場へのアプローチです。
円満な育休取得のために、計画的に進めましょう。
ステップ1:情報収集と意思決定
まずは、ご自身の職場の就業規則を確認しましょう。
育児休業に関する規定や、独自の支援制度(例:独自の給付金、休業期間の延長など)が設けられている場合があります。
また、過去に男性看護師が育休を取得した事例があれば、どのように取得したのか、周囲の反応はどうだったかなどを、可能であれば同僚や先輩に聞いてみるのも良いでしょう。
これらの情報をもとに、いつから、どのくらいの期間育児休業を取得したいのか、家族(特にパートナー)とよく話し合って決めましょう。
ステップ2:職場への相談タイミングと伝え方
育児休業取得の意向は、できるだけ早い段階で直属の上司に伝えるのが理想です。
法律上の申出期限は1か月前(産後パパ育休は2週間前)ですが、業務の調整や代替要員の確保などを考えると、安定期に入った妊娠中期(5~6か月頃)や、遅くとも休業開始予定日の2~3か月前には相談を始めるのが望ましいでしょう。
伝える際は、以下の点を明確に、誠意をもって話すことが大切です。
- 育児休業を取得したい旨とその理由: なぜ取得したいのか、家族にとってどれほど重要かを具体的に伝える。
- 希望する休業期間: いつからいつまで取得したいか。
- 業務の引継ぎについて: 担当業務の状況や、引継ぎの計画案を提示できると、上司も安心します。
- 職場への配慮: 休業中の業務への影響を最小限に抑えたいという姿勢を示す。

ステップ3:円満取得のための交渉術
上司や人事担当者との交渉を円滑に進めるためには、以下の点を意識しましょう。
- 協力的な姿勢: 一方的に権利を主張するのではなく、職場の状況も理解し、協力して調整していく姿勢を示す。
- 代替案の検討: もし希望通りの期間が難しいと言われた場合でも、代替案(期間の短縮、分割取得など)を検討する柔軟性を持つ。
- 周囲への根回し: 事前に同僚に相談し、理解や協力を得ておくことも有効な場合があります。
- 記録を残す: 相談した日時、内容、決定事項などをメモに残しておくと、後々の認識違いを防げます。
もしも「取得しにくい」と言われたら?
残念ながら、育児休業の取得に難色を示されたり、不利益な取り扱い(パタニティ・ハラスメント)を受けたりする可能性もゼロではありません。
そのような場合は、一人で悩まず、以下の相談窓口を活用しましょう。
- 職場の相談窓口: ハラスメント相談窓口や人事部など。
- 労働組合: 加入している場合は、労働組合に相談する。
- 都道府県労働局雇用環境・均等部(室): 専門の相談員が対応してくれます。(出典:厚生労働省 各都道府県労働局)
- 弁護士: 法的な対応が必要な場合。

そうだよね…。
一生懸命交渉しても、どうしても難しい時ってあるかもしれない…。
でも、そこで諦めないで!パパナースが輝ける場所はきっと他にもあるはずだよ!
そんな時は、一人で抱え込まずに、具体的な情報収集を始めてみるのがおすすめです。
例えば、看護師専門の転職エージェント「ナースジョブ」では、キャリアアドバイザーがあなたの状況や希望を丁寧にヒアリングし、育児に理解のある職場探しをサポートしてくれます。
非公開求人や、職場の雰囲気といった詳しい情報も得られるかもしれません。
》「ナースジョブ」で育児に理解のある職場を相談してみる
また、ご自身で多くの求人を比較検討したい場合は、「ジョブメドレー」のような医療介護専門の大手求人サイトも便利です。
「男性看護師歓迎」
「育休取得実績あり」
「時短勤務可」
といった条件で、あなたの希望に合う求人を効率的に探すことができます。
》「ジョブメドレー」でパパが働きやすい求人を探してみる
これらのサービスを活用して、あなたが安心して育児休業を取得できたり、復帰後に育児と仕事を両立できたりするような、より良い環境を見つけるための一歩を踏み出してみましょう。
4. 育児休業中の過ごし方と復帰への準備
無事に育児休業を取得できたら、いよいよパパとしての生活がスタート!
この期間をどう過ごすか、そしてスムーズな復帰のために何ができるかを考えましょう。
家族と向き合う貴重な時間
育児休業中は、生まれたばかりの子どもとじっくり向き合える貴重な時間です。
おむつ替え、沐浴、寝かしつけなど、積極的に育児に参加しましょう。
夜間の授乳(ミルクの場合)や夜泣き対応など、パートナーと協力して乗り越えることで、夫婦の絆はより一層深まります。
また、煩雑になりがちな出生届や児童手当などの手続きを率先して行うのもパパの重要な役割です。

スキルアップ・情報収集も可能
育児の合間に、自身のスキルアップや情報収集の時間を持つことも可能です。
- オンライン研修・セミナー: 看護技術や知識に関するオンライン学習。
- 資格取得の勉強: 認定看護師や専門看護師、ケアマネージャーなど、キャリアアップに繋がる資格の勉強。
- 最新の医療情報の収集: 学会誌や専門書を読む。
- 復帰後の働き方に関する情報収集: 時短勤務や部署異動など、復帰後の働き方について調べる。
ただし、育児が最優先であることを忘れずに。無理のない範囲で計画的に進めましょう。
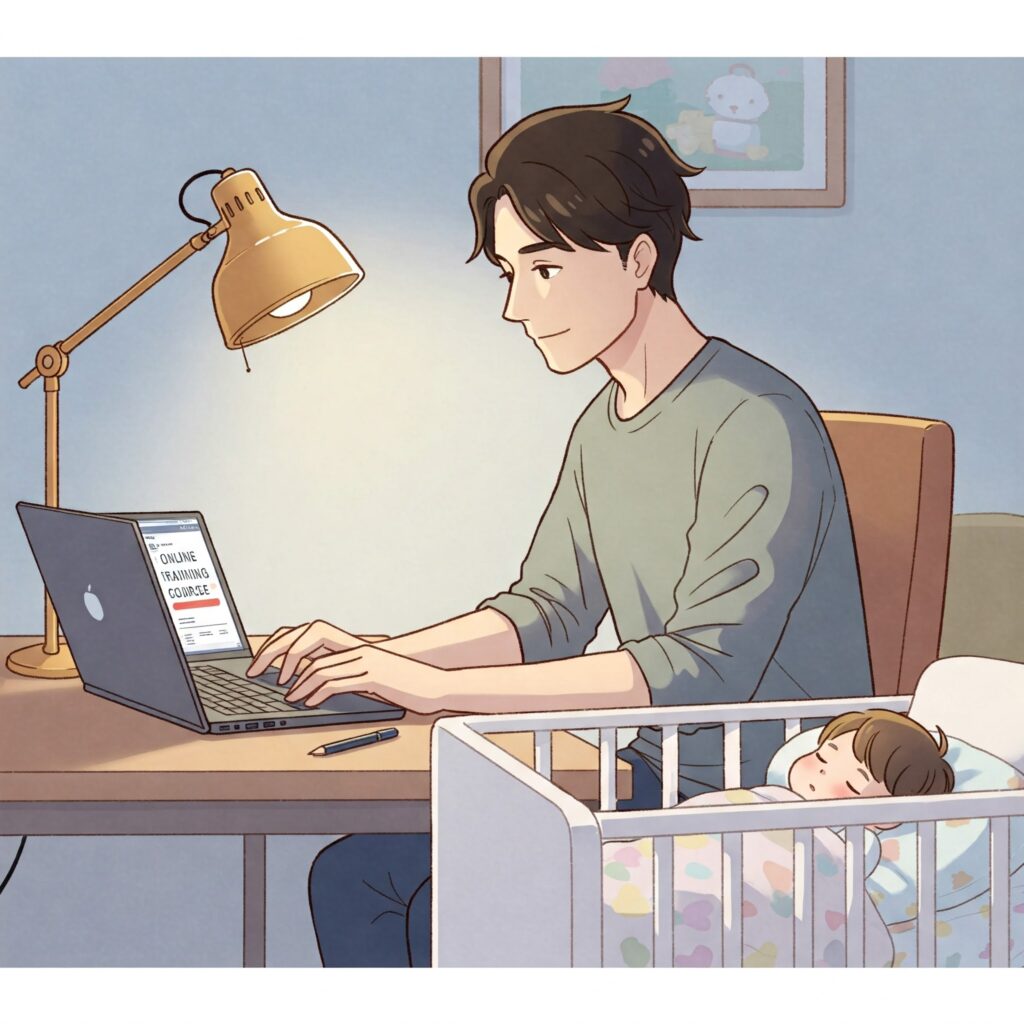
スムーズな復帰のために:復帰前面談
復帰が近づいてきたら、職場(上司や人事担当者)と復帰前面談を行うことが重要です。
- 復帰後の働き方の希望を伝える: 時短勤務、残業制限、夜勤の可否、部署異動の希望などを具体的に伝えます。
- 休業中の状況共有: 職場の変化や業務内容の変更点などを確認します。
- 不安な点の相談: 復帰に対する不安があれば、正直に相談しましょう。
この面談を通して、復帰後の働き方について具体的なイメージを共有し、スムーズな職場復帰を目指します。

育休中は、赤ちゃんとラブラブ💕な時間も大切だけど、自分のための時間も少し持てると良いですね😊
復帰前面談は超重要!
ここでしっかり希望を伝えて、不安を解消しておくのがスムーズな復帰の鍵です🔑
5. 復帰後の働き方:キャリアと育児の両立
育児休業からの復帰は、新たな働き方のスタートラインです。
ここでは、キャリアと育児を両立させるためのヒントを探ります。
多様な働き方の選択肢を知ろう
育児・介護休業法では、3歳未満の子を養育する労働者に対して、以下のような措置を講じることが事業主に義務付けられています(または努力義務)。
- 短時間勤務制度(時短勤務): 1日の所定労働時間を原則として6時間に短縮する制度。
- 所定外労働(残業)の制限: 労働者が請求した場合、残業をさせてはならない。
- 深夜業の制限: 労働者が請求した場合、深夜(午後10時~午前5時)に働かせてはならない。
- 子の看護休暇: 子どもの病気やケガの看護のために、年次有給休暇とは別に休暇を取得できる制度(小学校就学前まで)。
これらの制度を活用することで、保育園のお迎えや子どもの急な発熱などにも対応しやすくなります。
ただし、夜勤の免除や部署異動については、法的な義務ではなく、職場の規定や状況によって対応が異なります。
復帰前面談などで、ご自身の希望と職場の制度をよく確認しましょう。
パパナースが働きやすい職場の特徴
男性看護師が育児と仕事を両立しやすい職場には、以下のような特徴が見られます。
- 男性の育児休業取得実績が豊富: 周囲の理解があり、取得しやすい雰囲気がある。
- 柔軟な勤務体系: 時短勤務、フレックスタイム制、日勤常勤など、多様な働き方が選択できる。
- 男性看護師が多く在籍: ロールモデルとなる先輩がいたり、相談しやすい環境がある。
- 院内保育所などの福利厚生が充実: 子育て支援制度が整っている。
- チーム内の協力体制: 急な休みにも対応できるような、情報共有やサポート体制が整っている。
- 残業が少ない・管理されている: 定時で帰りやすい雰囲気がある。

育児経験をキャリアに活かす道
育児休業や子育ての経験は、決してキャリアのブランクではありません。
むしろ、看護師としての幅を広げる貴重な経験となり得ます。
- コミュニケーション能力の向上: 子どもやパートナー、他の親との関わりを通して、多様な相手とのコミュニケーション能力が磨かれます。
- 共感力・傾聴力の深化: 子どもの気持ちに寄り添う経験は、患者さんやその家族への共感力を高めます。
- タイムマネジメント能力: 限られた時間で家事・育児・仕事をこなす経験は、効率的な時間管理能力を養います。
- 小児看護・家族看護への関心: 自身の経験から、小児科や産婦人科、あるいは家族支援に関わる分野への興味が湧くかもしれません。
育児経験を通して得たスキルや視点を、今後のキャリアプランに積極的に組み込んでいきましょう。

復帰後の働き方、選択肢がたくさんあるんですね!✨
時短勤務や残業制限は心強い味方💪
働きやすい職場の特徴、要チェックです!
育児経験がキャリアにプラスになるって、すごくポジティブな考え方で素敵😊
6. 育児休業取得が難しい・両立が困難な場合の選択肢:転職という道
制度を活用し、職場と交渉しても、残念ながら育児休業の取得が難しかったり、復帰後の両立が困難だったりするケースもあります。
そんな時は、より良い環境を求めて「転職」を考えるのも一つの有効な選択肢です。
「転職」で叶える理想のワークライフバランス
転職によって、以下のような希望を叶えられる可能性があります。
- 男性の育休取得に理解・実績のある職場へ: 制度利用の心理的ハードルが低い。
- 柔軟な働き方が可能な職場へ: 時短勤務、日勤常勤、残業少なめなど、希望に合った働き方を選べる。
- 通勤しやすい職場へ: 通勤時間を短縮し、家族との時間を増やす。
- 子育て支援が手厚い職場へ: 院内保育所や手当など、福利厚生が充実している。
- キャリアチェンジ: クリニック、訪問看護、企業看護師など、夜勤のない働き方や、これまでと違う分野へ挑戦する。
今の職場で無理をし続けるよりも、環境を変えることで、あなたと家族にとってより良い未来が開けるかもしれません。
男性看護師の転職市場と求人の探し方
近年、男性看護師の需要は高まっています。
特に、体力や精神力が求められる救急、ICU、精神科などの分野や、手術室、整形外科などで活躍が期待されています。
また、訪問看護ステーションや介護施設でも男性看護師のニーズは増えています。
求人を探す際は、以下の点に注意しましょう。
- 病院・施設のウェブサイト: 理念や特徴、福利厚生、男性看護師の活躍状況などを確認。
- 看護師専門の転職サイト: 「男性看護師歓迎」「育児支援あり」「残業少なめ」などの条件で絞り込み検索が可能。
- ハローワーク: 地域密着型の求人が見つかる場合がある。
転職を考える際には、これまでのキャリアやスキルを見つめ直す良い機会でもあります。
もし、育児休業期間を含め、現場から離れていた期間(ブランク)があることに不安を感じる場合は、こちらの記事も参考になるでしょう。
ブランクからの復職を成功させるための具体的なステップや支援制度について解説しています。
-

-
ブランクがあっても大丈夫!看護師の復職を成功させるポイントと支援制度【2025年9月最新版】
「子育てが一段落したから、もう一度看護師として働きたい」 「違う仕事も経験したけど、やっぱり看護の仕事が好き」 「家族の介護が落ち着いたので、社会との繋がりを取り戻したい」 様々な理由で一度現場を離れ ...
育児との両立を最優先にした転職先の選び方
パパナースとして転職先を選ぶ際は、給与やキャリアアップだけでなく、以下の点を最優先に考えましょう。
- 勤務時間・勤務形態: 時短勤務は可能か、残業はどの程度か、夜勤の頻度や免除は可能か、日勤常勤のポストはあるか。
- 休日・休暇: 年間休日数、有給休暇の取得しやすさ、子の看護休暇などの制度は整っているか。
- 職場の雰囲気: 男性の育休取得実績、子育て中のスタッフへの配慮があるか(面接や見学で確認)。
- 子育て支援制度: 院内保育所の有無、保育料補助などの福利厚生。
- 通勤時間: 無理なく通勤できる距離か。
面接では、育児と両立したいという希望を正直に伝え、具体的な働き方についてしっかり確認することが重要です。
転職エージェントを賢く活用しよう
「働きながら転職活動をする時間がない」
「自分に合った求人の見つけ方が分からない」
という方には、看護師専門の転職エージェントの活用がおすすめです。
- 非公開求人の紹介: 一般には公開されていない好条件の求人を紹介してもらえることがある。
- 内部情報の提供: 職場の雰囲気や残業時間、育休取得実績など、個人では得にくい内部情報を提供してくれる。
- 履歴書・職務経歴書の添削、面接対策: 選考通過率を高めるためのサポート。
- 条件交渉の代行: 給与や勤務条件など、自分では言い出しにくい交渉を代行してくれる。
- 相談相手: キャリアプランや働き方の希望について相談に乗ってくれる。
複数のエージェントに登録し、自分に合ったキャリアアドバイザーを見つけるのが成功の秘訣です。


今の職場で頑張ることも大切だけど、どうしても難しい時は転職もアリ!👍
自分の希望条件、特に育児との両立を最優先に考えるのがポイントですね。
転職エージェントは心強い味方になってくれそう!✨
7. まとめ:パパナースが輝く未来のために
男性看護師が育児休業を取得し、復帰後もキャリアと家庭を両立させることは、もはや特別なことではありません。
社会全体の意識改革が進む中、医療現場においても、多様な働き方を認め、支え合う環境づくりが求められています。
この記事では、男性看護師の育児休業取得に関する制度、準備、交渉術、そして復帰後の働き方や転職という選択肢について解説してきました。
重要なポイントを再確認しましょう。
- 制度を理解し、権利を活用する: 育児・介護休業法、産後パパ育休、育児休業給付金などを正しく理解しましょう。
- 早めに準備し、誠実に交渉する: 計画的に準備を進め、職場と良好なコミュニケーションを図ることが大切です。
- 多様な働き方を検討する: 時短勤務や残業制限などを活用し、無理のない働き方を見つけましょう。
- 育児経験をキャリアに活かす: 子育てを通して得たスキルや視点は、看護師としての成長に繋がります。
- 時には転職も視野に入れる: どうしても現職で両立が難しい場合は、より良い環境を求めて転職を検討しましょう。
あなたが育児に積極的に関わることは、あなた自身、家族、そして職場にとってもプラスになります。
自信を持って、一歩を踏み出してください。
より良いワークライフバランスを求めて転職を考えるなら、看護師専門のナースジョブが力強い味方になります。
育児休業取得に理解のある職場や、時短勤務、日勤常勤など、あなたのライフスタイルに合わせた働き方ができる求人がきっと見つかるはずです。
子育て支援が充実した職場の情報も豊富なので、安心して新しいスタートを切れるでしょう。
パパナースが育児も仕事も楽しみながら輝ける、そんな未来を応援しています!
さらに、ご自身で多くの求人情報を比較検討しながら、納得のいく職場をじっくり探したいパパナースの皆さんには、「ジョブメドレー」のような医療介護専門の大手求人サイトも大変役立ちます。
「ジョブメドレー」では、
- 「男性看護師歓迎」や「育児理解あり」の求人も探せる: 「パパ活躍中」「育児休業取得実績あり」「時短勤務OK」「日勤のみ」など、男性看護師が育児と両立しやすい条件で求人を細かく検索できます。
- 多様な働き方の選択肢が見つかる: 病院だけでなく、クリニック、訪問看護ステーション、企業など、あなたのライフスタイルやキャリアプランに合わせた多様な職場の求人が豊富に掲載されています。
- 職場の雰囲気や制度もチェック可能: 求人情報には、福利厚生や子育て支援制度の詳細、職場の雰囲気などが記載されていることも多く、応募前にしっかりと情報を吟味できます。
- 自分のペースで直接アプローチ: 気になる求人が見つかれば、サイトから直接応募することができます。まずは情報収集から始めたいという方にもぴったりです。
「家族との時間を大切にしながら、看護師としてのキャリアも諦めたくない」
というパパナースの皆さんは、ぜひ「ジョブメドレー」で、あなたとご家族にとって理想的な働き方ができる職場を探してみてください。
》「ジョブメドレー」でパパナースを応援する求人を探す
参考文献・参考情報
この記事を作成するにあたり、以下のような信頼性の高い情報源に見られる情報を参考に、男性看護師の育児休業取得と復帰後の働き方に関する一般的な内容を構成しました。
特定の情報源の主張をそのまま掲載するのではなく、複数の情報を比較検討しています。
最新かつ詳細な情報(制度の内容、給付金の条件、各種手続き、求人情報等)については、必ず各公式サイト等で直接ご確認ください。 URLは変更される可能性がある点にご留意ください。
- 厚生労働省ウェブサイト
- URL:
https://www.mhlw.go.jp/ - (参考にした主な関連情報例):
- 育児・介護休業法の制度概要、改正内容に関する情報
- 産後パパ育休(出生時育児休業)の詳細
- 育児休業給付金(出生時育児休業給付金含む)の支給要件・手続き
- 雇用均等基本調査(男女別の育児休業取得率など)
- 職場におけるハラスメント(パタニティハラスメント含む)防止対策に関する情報
- 各都道府県労働局(雇用環境・均等部(室))の連絡先・相談窓口情報 など
- URL:
- ハローワーク インターネットサービス
- URL:
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/ - (参考にした主な関連情報例):
- 育児休業給付金の具体的な申請手続き、必要書類に関する情報
- 雇用保険に関する情報
- 看護師を含む求人情報の検索 など
- URL:
- 日本看護協会ウェブサイト
- URL:
https://www.nurse.or.jp/ - (参考にした主な関連情報例):
- 看護職の働き方改革、ワークライフバランス推進に関する情報・提言
- 看護職のキャリア支援に関する情報
- ハラスメント対策に関する情報・相談窓口 など
- URL:
免責事項
本記事は、男性看護師の育児休業取得や働き方に関する情報提供を目的としたものであり、特定のキャリアパスや転職、制度利用の可否を保証・推奨するものではありません。
各種制度の利用条件や手続き、職場の規定は変更される可能性があります。
必ず厚生労働省やご自身の職場の最新情報をご確認いただき、最終的な判断はご自身の責任で行ってください。
また、法律に関する具体的な相談は、専門家(弁護士や社会保険労務士など)にご相談ください。